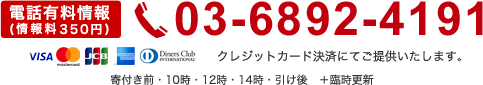昨年は日経平均の年足が陰線になってしまい、大納会の終値も4年ぶりに前年末を下回りました。日経平均は自民党総裁選が行われた2021年9月につけた3万795円がアベノミクス相場が始まって以降での最高値となったので、まさに岸田体制がスタートした場面が天井ですから、日本株は岸田政治がのしかかっていることがハッキリと分かります。
今年春に日銀総裁が交代して、政府主導でアベノミクスの金融緩和路線から転換していく方向になるというのが私も含めて大多数の見方です。したがって国策で国内の金利が上がっていくトレンドですから、銀行株が大きく値上がりしたのは今年の日本経済の方向を指し示したと言えます。
今週は18日の昼に日銀の金融政策決定会合の結果が発表されましたが、市場関係者や投資家の見方は分かれていた中で、早見は18日の朝寄り付き前の有料情報で、「今回は現状維持を予想する」とハッキリお伝えしました。結果は読み通りの現状維持で、日経平均は18日に652円高と急上昇しました。
ただ今回は現状維持でしたが、大きなとらえ方としては2月に新しい日銀総裁の人事案が政府から国会に提示されるので、それを受けて春に次の政策修正に踏み込むことを予想しています。したがって銀行株の大きな上昇トレンドには変わりないとみています。
ドル円は今週127円台まで円高が進んでいましたが、日銀の現状維持決定で一気に131円台まで円安が加速したものの、あっさりとまた128円台に押し戻されています。これを見ると「日銀の金融政策修正が先送りされただけで、結局は引き締め方向への流れは変わらない。」と市場が読み切っていることがハッキリとうかがえます。
海外の株価は先頭を切って欧州の株価の値上りが目覚ましく、イギリスは2018年5月以来の高値、アジアでも香港が半年ぶりの高値、上海も昨年9月以来の高値になってきました。私は有料情報やラジオ番組などで、欧州の株価の強さが日米の株価の先行指標になる可能性があるので要注目だと指摘してきましたが、欧州株の強さは変わりありません。
米株はNYダウはザラ場最高値であった12月13日の3万4712ドルからの下げ幅の82%を戻しました。米小型株の指標であるラッセル指数の週足チャートでは、一昨年11月の最高値からその後の戻り高値を結んだ大きな右下がりの上値抵抗ラインを、今月ついに上に突破して大きなブレイクアウトの形になりました。米株はチャート的に本格転換できるか正念場に来ています。
※このコラムは今週木曜発行の会員向けレポートから抜粋したものになります。
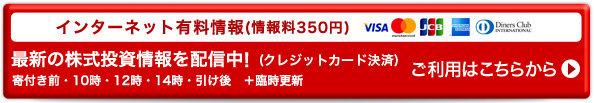

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷
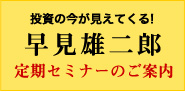
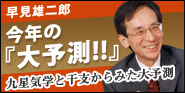
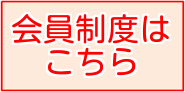
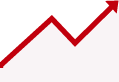
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.