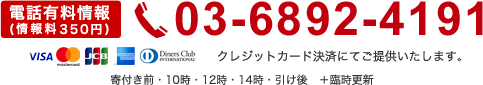今週は米国ではFOMC、日本は日銀の金融政策決定会合と日米の金融政策が最大の焦点でしたが、FOMCは市場の予想通り利上げが見送りとなりました。しかしFRBのパウエル議長は「米経済のソフトランディングはメインシナリオではない」と発言したことで、年内にまた1回追加利上げが実施される可能性が大きく意識されることになりました。このFOMCの結果を受けて米金利は更に上昇して、ドル円は昨年11月4日以来の148円46銭まで円安が進んでいます。米株はナスダック指数やSP500指数が一段と下げる展開になりました。
早見はこのところ一貫して、「日経平均など気にする必要はない。TOPIXの強さに目を向けよう」と言い続けてきました。実際日経平均は未だに6月につけた今年の最高値を抜けませんし、グロース指数とマザーズ指数も低迷したままです。しかしTOPIXは既に33年ぶりの高値になっていました。それだけでなくTOPIXコア30指数、日経300、東証プライム指数、スタンダード指数、東証大型株指数、中型株指数、小型株指数も先週から今週にかけて次々に新高値になりました。7月の最高値から調整安局面に入って下げが目立っていた米株とはまったく違います。
早見は投資作戦の中心を中大型株に置いてTOPIX型の投資作戦を進めてきました。半導体関連株やグロース市場の小型株などからは遠ざかっていたので、ナスダック指数や半導体株指数の下げによる影響は軽微の形になっています。
TOPIXの月足チャートは、1月の安値から今月で9本連続陽線です。これは2012年8月から13年4月までの9本連続陽線以来。つまりアベノミクス相場のスタートの時以来です。またTOPIXはこのままだと9ヵ月連続上昇となります。これは2005年5月から06年1月までの9ヵ月連続以来の記録になります。この時はちょうど2003年の大底から始まった小泉郵政改革ミニバブル相場でしたから、非常に強い形であることは歴然としています。
前回は阪神タイガースの優勝と株高の関係について解説しましたが、勘違いしてはいけないのは、阪神が優勝したから株価が上がるのではなく、株価が強い時になぜか阪神が優勝するのです。ですから結果として阪神が優勝した年は日本の株価も強いという関係になっているわけで、今年も同じです。
とはいえ、短期的な調整局面は常にあることですから、9ヵ月連続で上昇してくれば、当然下げる場面があっても何もおかしなことではありません。米株の下げがそうした自然なリズムを意識させる口実になる可能性は十分にあるので、淡々と受け止めながら見ていきましょう。
※このコラムは今週木曜発行の会員向けレポートから抜粋したものになります。
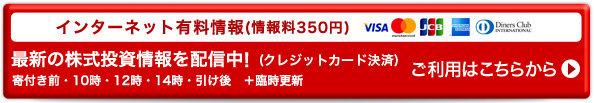

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷
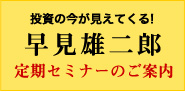
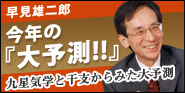
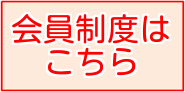
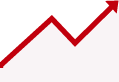
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.