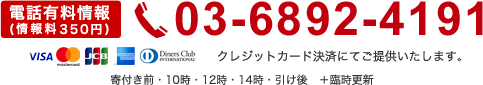ところがそこから一転して金利の上昇が株価を崩す形となり、18日に米株は急落して再び不穏な形になりました。米金利は17日に5年国債の利回りが1日としては7月以来の大幅な上昇となり、17年ぶりの水準になっています。
言うまでもなく金利が上昇するのは株価にとってはマイナスであり、それが限界を超えると大変厄介なことになるわけで、中東での地政学的なリスクの高まりが噴出したところに金利の上昇が重なり、米株がこれをどのように消化するかが大きな注目ポイントになっています。5%台の金利であれば、リスクを取って無理に株を買わなくても良いということになるのは自然なことです。
11月のFOMCでの利上げはほとんど考えなくても良いという見方が広がっていましたが、その後出てきた9月の米小売売上などが市場の予想を上回る強い数字だったため、再び金利の上昇が株価を圧迫する状況になっています。
もともと10月というのは株価の大きな下げ波乱が起きやすい時期で、歴史に残る2008年のリーマンショックや1987年のブラックマンデーの大暴落も10月に起きていました。今年も金利の上昇と中東情勢を踏まえて十分に注意しなければなりません。
一方、日本株についてはバンクオブアメリカが世界の機関投資家を対象に行なった10月の機関投資家調査によると、日本株への投資配分は5年ぶりの強気水準になりました。世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、9月に日本株の投資判断を中立から買いに引き上げました。相対的に日本株の優位性は世界の投資家が認識しているわけで、米株よりも強い動きを見せることが出来るか大いに注目されます。半導体関連株にも注目していますが、外部環境が波乱含みなので、ディフェンシブストックとして国内株に目を向ける必要もあります。
※このコラムは今週木曜発行の会員向けレポートから抜粋したものになります。
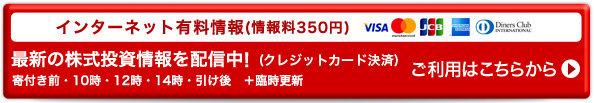

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷
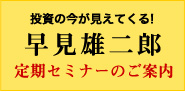
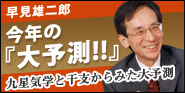
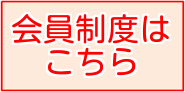
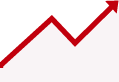
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.