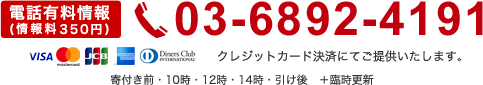当コラムを書いている20日の前場、NY原油は時間外で28ドルを割り込み、2003年9月以来の安値水準まで下落してきました。原油はまだまだ下げ止まりが見えず、世界経済の不透明感も増すばかりの地合いです。レベル感ではそろそろ自律反発を期待されてくるところですが、資源国通貨を筆頭にさえない展開が続いています。
横尾寧子のFXのはじめかた
利上げ消滅、一部利下げの可能性も言及2016.01.22
目先反発地合いも通貨は見極めが大切2016.01.15
欧米株の下落が一旦止まったことで、為替市場も反発局面となり、ドル円は11日に116円台まで下げたところが目先底値となって反転しています。原油安はまだ下げ止まりが見えないものの、年初から騰落率の大きかった豪ドル円(▲8%)、NZドル(▲7・5%)はやや自律反発の動きが伺えますが、カナダドル円(▲5・6%)などは反発力が弱いので、反発地合いではどの通貨を選ぶかよく見極めが必要になりますね。60分足にレジスタンスを引いて、乖離率とMACDを合わせて通貨ペアを見ています。ただ、年始からの動きは非常にボラタイルでテクニカルに頼ると一気にロスカットに到達するような地合いでしたから、あくまでも強弱を見極め、注目する通貨を見る1つの材料として参考程度に見るようにしています。
下げ止まり見えぬ南アランド2016.01.08
明けましておめでとうございます。今年は1月4日に世界が揃ってスタートになりましたね!皆様に良い1年になりますように。
さて、昨年末から振るわない南アフリカランドですが、まだ反発期待を持つのは時期尚早と思われる鈍い動きが続いています。
年の瀬に、NZドル上昇の兆し2015.12.30
2015年の取引が終わろうとしている今、NZドルに大きな変化が出てきました。
NZドルは今年、世界的な乳製品価格の下落に伴い、主要指数であるGDT価格が12年ぶりの低水準まで落ち込み、牧畜国の経済先行きに不安が高まりNZドル売りが強まりました。今秋以降は中国市場の中間層における高品質乳製品への需要の高まりと、中国の一人っ子政策廃止に伴う出生率増加見込みが後押ししてNZドルの反転上昇の機運となりました。
ポンドショート加速2015.12.25
12月の材料一服で、海外勢はクリスマス休暇が明けるまで積極的な取引はしてこない今、じわじわと下げが顕著になっているのが英ポンドです。
BOEは近年「次の政策対応は利上げだ」と発言をし続けており、米に続く利上げ期待通貨の位置付けを固めていましたが、一方インフレ率が高まることもなく、利上げ実施されることもないまま今年も終え、次第に利上げ期待が剥落していることが明白な動きになってきました。
中銀材料出尽くしも、円には先高観浮上か2015.12.18
日本時間、12月17日未明、FOMCは9年半ぶりに政策金利を25bp引き上げ、0・25-0・50%と決定しました。これ自体は高い確率で実施が見込まれ織り込まれていましたが、その後のイエレン議長の会見はタカハト両方が含まれており、市場(こと株式市場)をしっかり睨んでとんがらない内容になっていたという印象です。FOMCメンバーによる政策金利見通し=ドットチャートは、2016年末の政策金利が9月末時点よりもやや上昇し、1・375%で年4回の利上げ見込みがでるものの、2017年、2018年については据え置いたままとなり、市場を混乱させることなく無事通過となりました。
カナダドルが対ドルで2004年以来の安値へ2015.12.11
原油価格の下落が止まりません。12月8日のNY時間では、一時36・64まで下げたことで、資源国通貨が軒並み安の展開になっています。北海油田を持つノルウェークローネは2002年以来の安値、カナダドルは2004年以来の安値、ロシアルーブルも安値追いが続いています。
利上げの先は?2015.12.04
4日に発表される米雇用統計へ、いよいよ今年の為替相場のクライマックスが近づいてきました。11月の米雇用統計が順調であれば、16日の利上げは間違いなく行われ、利上げ幅とペースが今後の焦点になるかと思います。今回の米雇用統計の予想数値は、失業率が5・0%で前回と横ばい、NFPは20万人増で、前回の27万1千人を下回るという見通しですから、予想から大きく下にかい離するようでなければ利上げとなりそうです。
いよいよ年末相場へ2015.11.27
今週26日(木)は、米感謝祭で休場です。翌金曜日はブラックフライデーと言われるSALEが始まり、クリスマス商戦に向けた小売り購買動向を見る上で注目されます。そして最近ではオンラインショッピングが拡大していることから、感謝祭週明けの月曜日をサイバーマンデーと言い、オンライン売上にも注目が集まります。近年は原油価格の下落が消費を押し上げるという解説が見られたこの時期の小売りですが、今年はどうなるでしょうか。
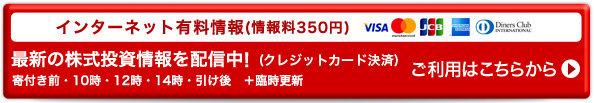

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷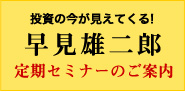
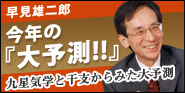
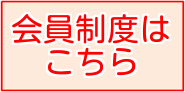
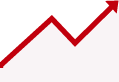
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.