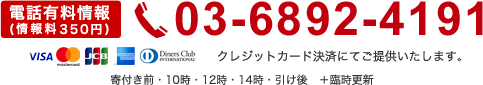先週末に浮上したキプロスの財政問題を受けて、週明けは円高・株安と不安を誘うスタートになりましたが、蓋を開けてみれば良い押し目を作ってくれた・・・そんなマーケットの強さを改めて浮き彫りにされるような結果となりました。
キプロス問題は、10万EUR以下の小口預金者に対する課税への反対が強く、キプロス議会は採決で否決と、当初の思惑では非常に最悪な結果をたどっているにもかかわらず、NYダウもFOMCの景気判断上方修正を受けてじり高となり、今の金融市場をけん引する二大市場である日米がネガティブな内容もすかさず吸収して跳ね返す様相が続いています。
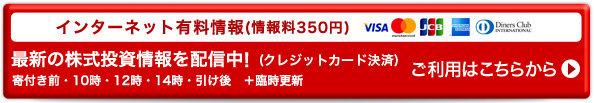

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷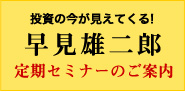
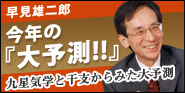
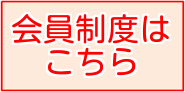
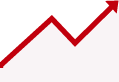
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.