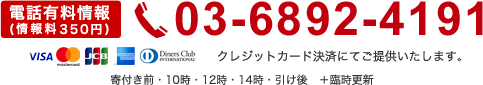先週末は、日銀の次期総裁に全く名前が取り沙汰されていなかった植田氏の指名報道で市場が波乱の動きになりました。現在の金融政策に対するスタンスが全く不明な状態での浮上でしたから、第一報に対するファーストアクションはドル売りの警戒ムードでしたが、同氏が記者団に対し「現状では金融政策の継続が必要だ」とコメントしたことで安心感から一気に買い戻しに。今週は改めて政府が正式に国会にて指名し、日本の日銀総裁人事は収束しました。就任後の最初の日銀金融政策決定会合は4月27-28日です。
横尾寧子のFXのはじめかた
年内の利下げ転換懸念後退2023.02.17
3ヵ月続いた円高ドル安に変化か2023.02.10
相場の流れが変わるとき、それは色々な要素がありますが、今回は2月3日に発表された米1月の雇用統計が大きなトリガーになったようです。
1月の雇用統計はNFPが予想+18.5万人に対して、結果+51.7万人と予想を遥かに上回る好数値。特にこのところ報道で目立つのは大手IT企業の人員削減やレイオフだっただけに、この数値には大きなインパクトがありました。失業率は予想3.6%に対して、結果3.4%と1969年5月以来約53年ぶりの低水準まで低下するという記録的な数値です。半世紀ぶりの好結果にドル円相場は一気に21日線を突き抜けて130円台乗せとなり、週明けには窓を開けての高値132.90迄上昇しました。
ユーロドルの戻りを参考に2023.02.03
アメリカは1日、今年最初のFOMCで政策金利を予想通り引き上げる決定をしました。利上げ幅は25bpで2会合連続で利上げ幅縮小したことも予想通りです。今回の決定で政策近位は4.50-4.75%となりましたが、FOMCメンバーが想定する年末の政策金利推移が5.1%であり、パウエル総裁は関係の中で「後2回ほどの利上げを協議中」であるとしました。米株は会合まで大きく値を消していましたが、会合が通過して議長会見が行われる中で値を戻す動きになりましたが、ドル円は一時130円台まで戻していたのが再び128円台まで値を消し、151円からの高値を結んだ右下がりの上値抵抗ラインを突破していたが勢いは続かず、21日線に頭を抑えられて再び失速の動きになっています。
カナダが先じて利上げ幅縮小へ2023.01.27
1月25日に行われた金融政策会合で、カナダ中銀は25bp、政策金利4.5%を決定しました。利上げは8会合連続、利下げ幅はこれまでの50bpから縮小しました。加速するインフレに対応するために急ピッチでの利上げを行ってきたが、今年はインフレが落ち着く見通しであることを述べ、利上げの打ち止めを示唆しました。また総裁発言の中では経済が強いこと、状況に応じた対応をすると今後の利上げの可能性を100%消すものではなくバランスの取れた内容でした。既に予想されていた内容で決定されたことから、カナダドルは大きな下落等にはなっていません。
日銀発表で強烈な買い戻しも勢い続かず2023.01.20
今年最初の日銀金融政策発表は、11時40分に「現状維持」と素早い判断がなされ、ドル円は128円台から一気に131円迄2.5%上昇、300pips以上の値上がりとなり、強い切り返しになりました。その後黒田総裁の会見(15時半~)以降は値をしていきましたが、日銀への「過度な」期待によるポジションの傾きが修正された形です。ただ、この動きは一時的で欧州時間には円高地合いが強まり、その後の欧米の経済指標の結果を受けて値を消し、結果行って来いの形になりました。日銀の内容は事前予想通りです。思惑が行き過ぎた結果の高いボラがありましたが、むしろそこは良い投資機会になったと言えますね。実際の黒田総裁の会見を見ると、今回は特段の変更も行わず、大規模緩和についてのスタンスは変えていませんが、YCC撤廃について否定はしていませんでした。未来についての否定もしていませんから、新体制に向けて再び思惑は出てくると思います。
年前半は日銀の変化に逐一反応2023.01.13
明けましておめでとうございます。今年もお正月からドル円相場が129円を割り込む相場地合いからのスタートとなりました。2022年は歴史的な円安相場をまさに眼前に見る貴重な1年でしたが、今年もまたドラスティックな動きが期待されます。コロナ前の「ドル円は年間で10円幅も動かない」という数年が嘘のようなボラティリティを発揮し、FXに新規参入される投資家さんも増えました。今年は監修させていただいた初心者向けFX本も発売になりますので、どうぞFXが気になるけれども及び腰な方にも手に取っていただければ幸いです。
来年も活況のドル円相場は続くのか2022.12.30
今年の為替市場では1年通して「インフレ抑制」がテーマとなり、各国中銀が相次いで低金利政策を撤回して利上げに転換していきました。ドル円相場は歴史的な151円台まで円安が進み、FX店頭取引高は今年の1月-11月までの累計で1京1083兆円!ちなみに昨年は1年間で5998兆円ですから、ほぼ2倍の取引高です。この内、ドル円相場だけで全体の74%を占める8223兆円に達し、かつてないほどFX取引が活発に行われたことが分かります。そのFX活況をけん引したのは円安相場ですが、さて来年はどのような動きになっていくのでしょうか。
更なる変更を否定した総裁、信じない金融市場2022.12.23
欧米がクリスマス一色に向かう今週、日銀が今年2回目の「サプライズ」を発表しました。1回目は当然、NY時間に行ったステルス介入です。あれも時間・曜日共にサプライズで円安を止める大きな要因になりましたが、今回もやってくれました。日銀は長期金利の変動許容幅の上限を0.25%から0.5%程度に引き上げる緩和修正を決定しました。大規模緩和をけん引してきた黒田総裁の春まで残り僅かの任期の中、ここへきて緩和修正という先行きを示すような大きな決定がなされたのはサプライズです。年明け以降、徐々に出口戦略、新体制に向けて日銀側が「におわす」発言をしてくるイメージでしたが、そうした市場の雰囲気を一蹴するようにしっかり決定してきました。ブルームバーグによると、今回の日銀の決定についてUBSアセット、シュローダー等3社は正確に予想したポジションを取っていたと報じられています。2008年のリーマンショック直後から以降の為替相場の方向性についても、当時UBSは先を見据えた正確な見通しを示している印象でした。今後も重要な転換点が続く中で、アナリスト発言等注視されそうです。
年末の大イベントを通過し流動性も低下へ2022.12.16
12月のFOMCが事前予想通りの50bp利上げが決定されました。パウエル議長の発言内容は比較的タカ派で「今後も継続して行動していく」という内容が強くありましたが、サプライズは無かったことから相場はやや膠着した動きになりました。ドル円相場は12月2日に133.62迄円高が進んだ後反発して137円台まで戻していましたが、再び軟調な動きになり135円を挟んで小動きになっています。今回に関して言えば、FOMCの内容は想定通りで特段の反応を示しませんでしたが、その前に報じられた「日銀は来年4月に発足する新体制下で金融政策の点検や検証を同年中にも実施する可能性がある」という内容に円買いがやや進んだ格好です。任期を迎える黒田総裁に代わる新たな日銀総裁候補として、雨宮正佳副総裁(67)、前副総裁の中曽宏大和総研理事長(68)が有力視されていると近々で報じられています。両氏に関しては、下馬評では今の大規模緩和の方向性が大きく変わる可能性は少ないとされていますが、新体制での点検といった内容が報じられてくると、候補に挙がっていない人物の擁立も密かに進んでいる可能性も否めません。
世界的な利上げの波に分岐点2022.12.09
12月2日に一時133.62迄下げて200日線にタッチしてきたドル円相場ですが、200日線に支えられる形で値を保って反発しており、急激な円高は一服しています。来週はインフレ率公表、FOMCと注目材料が続き、FOMCでは利上げ幅を50bpに縮小することがコンセンサスになっています。この見通しはおおむね変更ないと思いますが、来年以降の金融政策の方向性についての言及がどのようなものになるか、市場の注目が集まると思います。
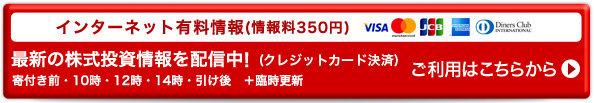

 文字サイズ
文字サイズ このページを印刷
このページを印刷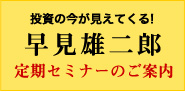
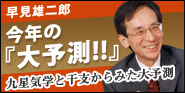
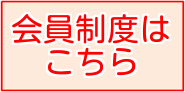
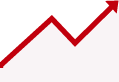
 Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.
Copyright © MEDIK Investment Advisory Co.,LTD, All Rights Reserved.